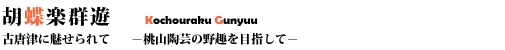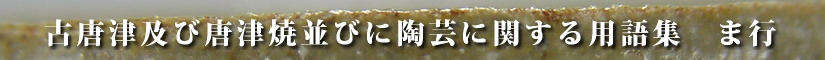古唐津及び唐津焼並びに陶芸に関する用語集 ま行
ま
マイセン
1709年にザクセン・マイセンの城内にできたヨーロッパ初のドイツの磁器工場。
益子焼(ましこやき)
浜田庄司の陶芸によって有名な、栃木県益子町の焼き物。褐色の鉄釉(てつぐすり)による甕(かめ)や擂鉢(すりばち)などの民具が中心。
斑唐津(まだらからつ)
藁灰釉をかけ、白く焼きあがるが、燃料の松灰が降りかかり青い斑文が出るところからこの名があります。
白灰色の釉と飴釉が斑にかかったものや、青みを帯びたむらのある白濁色の灰釉がかかったものをいう。
帆柱窯から出土するものに優れた作品が多くあります。。
徳利・ぐい呑のほか、「王」の刻印のある洲浜形の小鉢が古来茶人の間で好まれています。
藁灰釉をかけ、白く焼きあがるが、燃料の松灰が降りかかり青い斑文が出るところからこの名がある。
茶碗、皿、鉢、徳利、盃などがの製品があります。
斑唐津を焼いた窯としては、帆柱、岸岳皿屋、道納屋谷、山瀬などの岸岳系諸窯がよく知られていますが、櫨の谷、大川原、椎の峰、藤の川内、金石原、中の原、岳野、泣早山、阿房の谷、道園、焼山、市ノ瀬高麗神の諸窯でも焼かれていました。
斑唐津という名称は、釉薬の分類の名称で、稲科の植物で珪酸分の多い草や藁等燃やして灰を作り、それを主成分とした釉薬(白釉とも言う)が、元々白く焼上がるのだが高温度で土と熔け合い透明になったり微妙な色が発色したり変化に富み斑状になるのでこの名称が付いたようです。
この釉薬を単独で掛けたものを斑唐津、鉄分の多い飴釉と掛け分けたものを朝鮮唐津といいます。
古唐津の初期の頃より使われた釉薬で、北朝鮮の焼き物にルーツがあり、今日の陶磁器の世界では鉱物原料が大半を占める釉薬が使われていますが、この釉薬は身近で手に入りやすい茅や稲の灰を釉薬として使っていたと思われます。
元来、陶磁器は白さに憧れるのもですが、この斑唐津の白さも一種独特な面もちがあり、鉱物原料の長石や珪石の白さとは違う味があります。
よく「備前の徳利、唐津のぐい呑み」といわれますがこの「ぐい呑み」が斑唐津のぐい呑みといわれています。
斑釉(まだらゆう)(藁白釉-わらじろゆう)
斑唐津又は朝鮮唐津の白い方の釉薬で古唐津や唐津焼の重要な釉薬です。
イネ科の珪酸分が多い植物を燃やして灰にしたものや米の稲穂を取った藁を灰にした物を藁灰「ワラバイ」といい、主に木などの植物を燃やして灰にしたのを土灰「ドバイ」といい、白くて焼くとガラス化する石を粉砕したのを長石「チョウセき」、この三種類の原料を混ぜ合わせてふるいを通して良く混ぜ合わせて調合したものを藁白釉といいます。
高温で焼くと白い乳濁色になりますが、土や他の成分と溶け合い所々が透明になったり別の色を発色させたり、斑状(むら)になる為、斑唐津「まだらからつ」という名称になったといいます。
北朝鮮地方から日本に伝わってきたと思われます。
唐津焼の一大特色を有する釉薬である「斑釉」は古今の釉のなかでも、最も「高珪酸質」で反面、アルミナ成分は極めて少ない釉薬です。
「斑釉」は、珪酸質原料としては「稲藁」「籾」または「茅」の珪酸質の灰で、これらは灰化と炭化の中間物質が共存した状態で使用され、溶剤としては土灰で、その他若干の長石類または粘土類によって調整されています。
「斑釉」の特色としては、全体やや流下気味で白濁し、部分的または多数のスポット的な斑状の群れによる青味または透明性の流下し釉薬の表情が豊かな表情を表します。
窓絵(まどえ)
色々な形に区切った白い空間のことを窓という。そこに絵を描いたものを窓絵という。
俎皿(まないたざら)
脚つきの四方皿のことをこう呼びます。
その形が、俎(まないた)に似ていることからその名がつけられたようです。
松皮菱(まつかわびし)
菱形を3つ重ねた、向付(むこうづけ)の器形の一種。
.
み
三川内焼(みかわちやき)
長崎県佐世保市で焼かれた磁器で平戸焼とも呼ばれる。
朝鮮陶工によって藩窯(はんよう)として始まる。
見込(みこみ)
器の内面全体か、内面の中央部分のこと。茶碗などの内部の底のあたりのこと。
三島手(みしまて)粉青沙器印花(李朝15世紀)
別名は暦手(こよみで)。線彫りや印で押した花文を現す象嵌(ぞうがん)技法。もとは朝鮮李朝の技法。
三島の、線彫りや印で押した花文を現す象嵌(ぞうがん)技法によって焼かれた唐津焼。
朝鮮の陶磁器で、濃い鼠色の素地土白い化粧土で覆った一群の半磁半陶質のものをいいます。
三島は高麗青磁象嵌手の変化したものと思われ、手法や形状からいろいろの名称が付けられています。
彫三島・釘びり三島・刷毛目三島・絵三島・花三島・檜垣三島・礼賓三島・角三島・渦三島・御本三島・半使三島・堅手三島・伊羅保三島・黒三島・二作三島・三作三島などがあります。
これらは技法的に分類すると三種に分けられ、印花・刷毛目・彫紋です。
文様は暦手が最も多く、檜垣紋・印花紋・文字などがある。高麗雲鶴青磁に見られる飛雲・鶴・丸紋(狂言袴)・雁木・波紋などもみうけられるが、人物動物紋は見られません。
産地は忠清南道公州郡鶏龍山窯のほか八道一三六ヶ所と伝えられています。
名称は暦手に点綴された線条紋と花紋とを交えた文様が三島大社(静岡県)より頒付していた暦に類似しているためとするのが通説となっています。
慶長の役後、渡来した韓国南部地方の陶工たちによって伝えられた技法を示すものに三島唐津があります。
三島唐津には象嵌・刷毛目・型紙刷毛目などがある、いずれも白土を使用する点が共通しています。
なお韓国では1万のことを粉青と呼んでいます。
三島唐津(みしまからつ)
慶長の役後、朝鮮半島の陶工により上画の粉青沙器印花風(日本でいう三島手)が伝えられました。
鉄分の多い土は焼くと黒くなりますが、白く見せるために胎土の上に白土を使って化粧する技術が刷毛目、粉引であるが、刷毛目、粉引のままのものもありますが、白化粧のあと線彫りした彫三島・櫛を用いて文様を書き出した櫛刷毛目・染色の型紙を使って文様を描き出した型紙刷毛目・胎土のやわらかいうちに刻印を押たり、線彫りをして、白土、赤土を埋め込んだ象嵌・文様を掘り出した掻き落としなどの技法を用いて、唐津独特のものに発達し三島唐津になりました。
水挽き(みずひき)
粘土と接する手の滑りを良くするために、水を使って轆轤(ろくろ)を挽き成形すること。
手のすべりをよくするために、水をつけることからこの名があります。
水指(みずさし)
茶道具の一つ。
釜に補給するための水や、茶碗をすすぐための水を入れておくための蓋つきの器。
美濃焼(みのやき)
岐阜県の美濃地方東部で焼かれた陶磁器で、奈良時代の須恵器(すえき)から始まり、独自に志野(しの)、黄瀬戸(きぜと)、瀬戸黒(せとぐろ)を製作していました。
岐阜県東南部に広がる美濃窯の中で、土岐市の久尻から可児市の大萱にかけての一帯の窯は特に優れた桃山様式の焼物を焼いたことで知られています。
有名な「国宝志野の名碗 国宝指定の『卯花墻』」は、そうした作品のひとつで、大振りで筒形の力強い造形に、奔放な筆致で橋と苫屋が描かれています。
志野のなかでも古格の堂々たる作風を示す作品ですね。
国宝に指定された国産のお茶碗は2碗しかないんですが、この『卯花墻三井家所蔵』がその内の一つです。
もう一つは諏訪の「サントリー服部美術館」所蔵の白楽茶碗(銘不二山)本阿弥光悦作です。
深山路(みやまじ)
奥高麗茶碗・銘『深山路』をいいます。
茶道筌蹄(てんせい)※に「高麗人来たりて唐津にて焼し故高麗の方より奥といふ事なり」とあり、然れども奥は古きといふ意味なり。
此種の陶器肥前唐津にて焼しか、或は朝鮮の或る地方にて造りしか、今之を確知するに由なしと雖も、兎に角一手古きを以て奥高麗とは呼ぶなるべし。
而して深山路の銘は蓋し此奥と云ふに縁故をもとめたる者の如し。
『大正名器鑑』より
※筌蹄(てんせい)とは、魚を捕る筌(うえ)と兎を捕る蹄(わな)。目的が達成されると不要になるもの。目的を達成するために利用する道具・手段。
書籍:とんぼの本:唐九郎のやきもの教室(加藤唐九郎)の中にも紹介されています。
む
麦藁手(むぎわらで)
茶碗などに銹や染付(そめつけ)などで何本もの縦線を引いた文様を描いたもの。麦わらに見立てた縦線が特徴。
向付(むこうづけ)お向(おむこう)向(むこう)
向付とは簡単に言うと、日本料理の膳の向う側に置かれ、食膳に置く正面という位置からの名称で、正面中央に、主肴の容器として、茶事懐石では終始不動の位置を占めます。
現在の家庭では食卓に膳(折敷)を用いることは少なく、向付、お椀盛、焼肴、煮物と順序を決めることはしないが、そんな家庭料理にても向付は主要の座に置かれる場合が多い。
茶事懐石による向付はいつとなしに常套語として日常茶飯事に呼称するが、前期の如く最後まで定着するが故に、格別の用意し、四季折々に料理と兼合いで品定めするは当然です。
利休時代の茶事記録によれば、おかずの品数は少なく今日のように数々を振舞うことはなかったから向付は大振りであったようです。
現に伝来の志野向付も唐津向付も一個使いして鉢の用に足るものであり、径六寸(19センチ)もの大振りです。
村田珠光(むらたじゅこう)
応永30年(1423)~文亀2年(1502)。
父は奈良東大寺の検校村田杢一と伝えられ、称名寺の僧となる。
のち一休宗純に参禅し、その印可証明として「圜悟の墨跡」を与えられました。
「心の文」を著し、茶の湯を「道」としてとらえ、唐物の茶の湯に和物との調和を提唱し、わび茶の祖とされています。
め
名物(めいぶつ)
茶道具で、千利休の時代に名を得た名品を指す。
利休以前の、東山時代のものを大名物、利休以後の小堀遠州が選定したものを中興名物という。
銘々皿(めいめいざら)
もともとは懐石道具の一種。
各人に一客ずつ充てられる皿のこと。
目跡(めあと)
目痕(跡)ともいい、器物の見込みにある重ね焼の痕を言います。
器物の溶着を防ぐために、器物と器物の間に芽土(土塊)・砂・貝殻などを置くために生じます。
現代の窯詰めでは棚板という高温でも歪まない板の上に器物を並べ、その板を窯の上部まで段々に重ねて多くの器物を入れることが出来ますが、昔は現代のように窯道具が豊富ではなく床面でしか焼くところがなく数量も限られていたので、出来るだけ多くを焼くには器物を直接重ねる方法をとっていたようです。
その際器物同士が溶着しないよう高温にも強い土を器物間に挟むやり方で焼成し、その痕が残ったのを目痕といい茶人達が鑑賞したようです。
目積み(めづみ)
器を直接重ねていく、窯詰めの方法の一種。
釉などのひっつきが起きることを避けるために、小さな土の塊りや砂を挟むことをいいます。
この目積み(めづみ)の傷を目跡(めあと)と呼びます。
面取り(めんとり)
器表をヘラなどで削り取って、多角形にすること。また角の頂点を削り落とす技法のこと。
も
木盃形(もくはいがた)
鍋島の高台皿にみられる、丸みをもった立ち上がりの独特の形状。
シンプルな形状ではあるが、高度な轆轤の技術を要する形である。
元屋敷窯(もとやしきがま)
元屋敷窯跡は、古くから織部の名品を生産した窯として、また美濃窯で最古の連房式登窯として有名で、昭和42年に国の史跡に指定されています。
昭和5年荒川豊蔵氏により、瀬戸黒・黄瀬戸・志野・織部といった美濃桃山陶が、瀬戸ではなく美濃で生産されていたことが発見されると、美濃窯には乱掘に等しい大発掘ブームが起こります。
そのなかで、この元屋敷窯跡は当時の地主や地域の人の努力により大切に保存されてきました。
元屋敷窯跡からは戦前の多治見工業学校(現多治見工業高等学校)、戦後間もなくの美濃陶祖奉賛会による発掘で大量の織部焼が出土しています。
また昭和33年には名古屋大学考古学研究室により窯体が調査され、焼成室を14室もつ連房式登窯であることが確認されています。
しかし出土した遺物をみると、連房登窯が導入される前に生産されたと考えられる天目茶碗、皿類、擂り鉢や瀬戸黒、黄瀬戸、志野も多く含まれ、元屋敷窯(連房式登窯)に先行する大窯があるだろうと考えられてきましたが、なかなか遺跡の全体像を把握するには至りませんでした。
そこで平成5年、土岐市教育委員会が範囲確認調査を実施し、大窯2基(元屋敷東1・2号窯)と2号窯の上につくられた作業場所などの遺構を確認しました。
物原(ものはら)
窯の周辺にある、焼き損じなどを集中して廃棄したところ。
発掘品は、この中から出たものが多くあります。