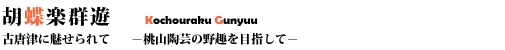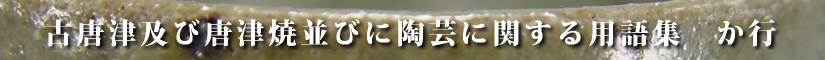古唐津及び唐津焼並びに陶芸に関する用語集 か行
か
貝高台(かいこうだい)
古くは、器物を重ね焼きするとき、熔着を防ぎ、また器の座りをよくし製品の歪を避けるため、器物の間に貝を置いて窯詰を行ったが、そのため高台に貝殻が付着したり、貝殻の形紋が付いたものをいいます。
朝鮮茶碗、唐津・上野・高取焼などに多く見られます。
昔、現代のように優れた窯道具が無かった時代、工夫を重ね、常々食していた貝の殻を使ってみて、貝殻の主成分である石灰は単独では高温(陶磁器を焼く温度)では熔けず形も崩れにくい性質であること、又これが焼きあがった後の処理がとても簡単で土や他の物では形は崩れないが硬く焼きしまっていて削り取りが大変だが、貝殻だと焼き上がった時は硬かったのが水に浸けると崩れ落ち後は器物との接着部分の鋭利な所を削るだけの手軽さを知り、土で作ったハマ(器物を乗せて焼く窯道具)の上に貝殻を敷き、その上に器物を乗せたやり方で窯詰を行っていたようです。
貝高台を使用するとその部分が窯変します。緋色が鮮やかに出ます。これを一般の商品に行えば、ムラが発生しますのでよくありませんが、1個づつ作る作品は味わいがある作品になります。
懐石(かいせき)会席(かいせき)
茶道の発達に伴い、茶事にふさわしい料理が考えられ、「懐石」と呼んだ。時代を経て転じて、宴会の料理を「会席」と呼ぶようになったようです。
和食店や日本料理店での懐石料理は禅門における本来の意味での懐石料理(精進料理)や茶を喫する為の料理、茶懐石料理から発展したものです
灰陶(かいとう)
中国・竜山文化期から殷・西周までの先史時代の土器の一種です。焼成の最後の段階で、燻し焼きで焼き締めたもの。朝鮮の百済土器や新羅焼、日本の須恵器が同じになります。
梅華皮(カイラギ)、梅花皮(かいらぎ)
釉(うわぐすり)がちぢれて粒状になった部分で、井戸茶碗(いどじゃわん)のように燃焼不足から高台脇の釉(うわぐすり)が溶けきれず鮫肌状(釉が縮れて粒状になった部分を言う。)になったものをいいます。
カイラギ梅花皮・鰄とも書き、カエラギ・カエラゲともいいます。
本来、「東南アジア原産の鮫類の皮で、アカエイに似た魚の背皮」を意味します。
その皮で、刀剣の柄や鞘や、装飾品に用いられました。
カイラギは本来刀剣の柄などを飾る蝶鮫の皮のことで、その白いざらめき肌が釉縮れに似ていることから、転用されました。
高台も削り出しが荒くなされた後釉をかけると、窯の中でその縮れた土皺の間に釉が結粒し、カイラギを生じやすくなります。
昔の茶人・数寄者等がそれを見いだし珍重し「カイラギ」と見立てて、その名称で今日にまで伝えられたのだと思います。
それらは現在まで唐津焼、萩焼のルーツとして現在まで受け継がれています。そのほかにも志野焼の中にも同じ様な模様をした陶器も見られます。特に有名なものとして古陶器の井戸茶碗など李朝系(朝鮮半島)の陶器が挙げられます。
焼き物を作る上で、はっきり言って釉薬では不良品だと思いますが、そういった不良品を日本人特有の美的感覚から美術工芸品として、茶の湯では景色として喜ばれれています。
蛙目粘土(がいろめねんど)
花崗岩類の岩石が風化して堆積したもので、カオリンを主成分とし、2~5・ほどの石英の粒子が入った粘土をいいます。
風化花崗岩が淘汰されることなく湖沼に堆積したカオリン質粘土層より、カオリナイトを主成分とする粘土を水簸(珪砂と粘土の分離)し、精製した可塑性粘土です。
蛙目粘土は、比較的大きな珪石粒(せきえいりゅう)(珪砂(けいしゃ))を含んだ堆積粘土で、雨が降って粘土が流れた後に、珪石粒が蛙(かえる)の目のように残っている姿から蛙目粘土と呼ばれるようになりました。
粘土と珪砂は約半分ずつ含まれており、水簸(すいひ)して粘土と珪砂を分離して、珪砂はガラス原料などに使用されます。
蛙目粘土は可塑性が高く比較的豊富に産出したため全国に出荷されています。
蛙目粘土も木節粘土と同様に炭化した木を含むためネズミ色に着色された粘土です。
花押(かおう)
記号もしくは符号風の略式の自署(サイン)で、判(はん)、書判(かきはん)、判形(はんぎょう)、押字(おうじ)などともいいます。
花押の起源は自署の草書体にあります。
これを草名(そうみょう)とよび、草名の筆順、形状がとうてい普通の文字とはみなしえないまでに特殊形様化したものを花押といいます。
花押の発生は中国にあって、その時期は遅くも唐代中期と見られています。
日本の花押も中国にならって用い始めたと考えられ、その時期は遺存史料の限りでは10世紀前半期ころのようです。
カオリン(かおりん)
磁器の原料である白色磁質の粘土の一種で、磁器(じき)に使う釉薬(ゆうやく)の原料として用いられ耐火度が高く粘り強い粘土鉱物で超微粒子の集合体です。
陶器で有名な中国の景徳鎮で使われていた陶土の産地、高陵(カオリン)村の名からカオリンと呼ばれています。
柿右衛門様式(かきえもんようしき)
伊万里焼(いまりやき)の一種。
濁し手(にごして)とよばれる白磁(はくじ)に赤絵の具を基調とし、余白をいかした優美な色絵磁器のことをいいます。
17世紀はじめに、国内で最初に磁器を作り出した肥前(ひぜん)地方で生産され、ヨーロッパに輸出されたもので、アメリカを経由して日本に里帰りした。
柿右衛門様式の磁器はヨーロッパで人気を博し、18世紀に入ってヨーロッパで最初に磁器の焼成(しょうせい)に成功したドイツ・マイセン窯をはじめ各地の窯で、コピー製品が作られました。
掻き落とし(かきおとし)
生乾きの素地(きじ)に黒色の土を塗り、一部を削り取り文様を描くという装飾法。中国磁州窯(じしゅうよう)の朝鮮李朝(りちょう)ものが有名です。
掻き落としは化粧土を使った装飾技法の中でも古くから一般的なものです。
中でも中国の磁州窯、高麗青磁、李朝の粉青沙器などが有名です。
志野焼の鼠志野、紅志野も酸化鉄を多く含む黄土を化粧土として使い、模様を掻き落としたもので、還元焼成すると鼠志野、酸化焼成すると紅志野になります。
柿の蔕(かきのへた)
高麗茶碗(こうらいぢゃわん)の一つ。李朝(りちょう)の初期に作られ、青みを帯びた釉(うわぐすり)が薄くかかった肌合が、柿の蔕(かきのへた)に似ているためその名がある。
その名の起こりは、文字通りその釉色が柿の蔕の色に似ていること、高台から見ると高台付近が柿の蔕のように見える事で、我が国の茶人が付けた名前です。
柿釉(かきゆう・かきぐすり)
酸化焼成で柿色に焼き上がる、褐色の鉄分の多い釉をいいます。
掛流し(かけながし)
なだれ状に、2~3種類の釉薬(ゆうやく)を柄杓などで流しかけること。
九州の小鹿田焼が有名です。
掛分け(かけわけ)
2種類以上の釉薬(ゆうやく)を器物の左右または上下に掛分ける装飾焼成技法の一つです。
鎹継ぎ(かすがいつぎ)
陶磁器の割れたのを接合するため割れ目に沿ってその左右に小穴をいくつかあけ、金銀などの小鎹で継ぎ合わせる修理法をいいます。
中国人の特技として知られています。
有名なのは、中国の南宋時代に作られた青磁茶碗の名品、その名も馬蝗絆(ばこうはん) ですね。
これは、南宋時代(12世紀)砧(きぬた)青磁の名品でした。
その後、時代は流れ室町幕府の第8代征夷大将軍、足利義政(15世紀中旬頃)の時代に過って、このお茶碗にひびを入れてしまい、当時の中国(明時代)に送り、代わりのお茶碗を要求したらしいのですが、これに代わる名品は作れないとして、当時の中国皇帝(明王朝)は、お茶碗に鉄の鎹(かすがい)で修理を施して返送したとされています。
どうしてこのお茶碗が「馬蝗絆(ばこうはん)」名付けられたのは、馬蝗(ばこう)とは馬の背中にとまった蝗(いなご)であり、中国で鎹(かすがい)の意味でも使われるため、このお茶碗の修理に使われた鎹(かすがい)を背中に泊まったイナゴに見立てて、この銘(名)がついたということです。
室町期の唐物数寄の中でも特別に評判が高かったらしく、通常、漆を糊代わりにして修理するところを、わざわざ目立つ鎹を用いていることから、器の価値を誇示する目的もあったと推定されています。
時代が数百年進んだにも関わらす昔の名品を再現させることが出来ない、中国の青磁が最高レベルに達したのが南宋時代(12~13世紀)と言われる所以です。
12世紀から15世紀の時代を超えて繰り広げられた中国と日本の美意識の高さを示す歴史物語の一つです。
片口(かたくち)
鉢の口縁に一ケ所注ぎ口があるもの。唐津の片口(かたくち)の中には、注ぎ口を欠いて侘茶の茶碗として用いるものもあります。
本来は油・酒・醤油などを入れて用いた雑器ですが、懐石で香物鉢に用いたり、小振りのものは茶碗に用いています。
一般に瀬戸系のものは注ぎ口の上に縁が無く、唐津系のものには縁があります。
注ぎ口を欠き共繕いしたものを「繋ぎ駒」、穴の残ったままのものを「放れ駒」といいます。
唐津の片口は新たな土で片口を造り穴を開け接着する作り方をしています。
この片口の造り方は唐津が日本では最初のようで片口と唐津とが代名詞ともいえるでしょう。
片口の口は、昔は用途として作っていたのですが、今日ではほとんど装飾的な意味合いで作っているのが多いようです。
茶道において片口を侘びの茶碗に用いることがありますが、これはほとんど唐津の茶碗に限られているようです。
型作り(かたづくり)
型に陶土を押し当てて成形するため、同形のものを量産するのに適した技法。
型抜き、型打ちともいいます。
堅手(かたで)
高麗茶碗(こうらいぢゃわん)の一種。素地(そじ)や釉色が堅い感じがその名の由来で、ほとんどが白地の茶碗。
李朝前期に作られたもので、土・釉ともに堅い感じがするため、堅手と呼んだものらしく、多くの窯で作られています。
形は井戸風の開きかげんの茶碗となっています。
普通は総釉であるが、代表的な長崎堅手では釉が裾で切れていたりすることがあります。
現在では、陶器・磁器と区別していますが、当時は、作り方は同じでも本来は窯の近くの土を使い焼成するため、区別しにく買ったため、結果的に焼きあがったものが磁器質のものを堅手と表現したのではないでしょうか。
片身替り(かたみがわり)
器の文様などが、左右または上下半分ずつ異なること。
焼成により、火表と火裏ができ、器の半分ずつで景色や調子が異なることがあります。
現在では、人為的に釉や絵付けを表と裏で変える装飾技法の一つとなっています。
型物伊万里(かたものいまり)
型を用いて成形した伊万里焼(いまりやき)。染付(そめつけ)・色絵(いろえ)に金彩(きんさい)を加え、唐草・幾何学的な小紋を組み合わせた文様構成が特徴。
褐釉(かつゆう)
中国の漢時代につくられた低火度釉の褐色の釉。
通常、緑釉・褐釉の総称として使われることが多いが、ここでは緑とも褐色ともつかない特有の釉楽について、この名称を用いています。
蕎麦釉などともよばれる鉄釉の一種です。
加藤唐九郎(かとうとうくろう)
16歳から作陶をはじめ、黄瀬戸(きぜと)、志野(しの)、絵唐津(えからつ)、伊賀(いが)など幅広くおおらかな作風が特徴の陶芸家、また陶磁史研究家。
1897年(明治30)7月19日は愛知県東春日井郡水野村(現・瀬戸市水野町)出身。
桃山時代の陶芸の研究と再現に努めました。
永仁の壺事件で、無形文化財の資格を失うなどの波乱も味わっています。
窯(かま)
窯とは一つの発熱装置であると同時に、発生した熱エネルギーを作品に伝えることによって、実用に耐えられるように胎土を焼固させ、また、施釉したうわぐすりを熔かし、その機能性を高めるとともに美的効果を促進させようとする道具(装置)です。
低火度(ていかど)の窯は、素焼窯・錦窯(絵付窯)であり、高火度の窯には本焼窯があります。
加守田章二(かもだしょうじ)
灰釉陶や象嵌(ぞうがん)、彩釉など多彩で独自の作陶をもった陶芸家。
陶芸家として初めて高村光太郎賞を受賞するなど、若くして陶芸界の注目を集めた作家でした。
白血病にて享年49才にて亡くなられました。
同じ病気の陶芸家としても尊敬している陶芸作家です。
唐子絵(からこえ)
中国人の子供を描いた図柄で、九州平戸の三川内焼(みかわちやき)で、松樹の下で遊ぶ唐子(からこ)の図が有名です。
松の木の下で無心に蝶とたわむれる中国の子供を描いた図柄で、別名「献上唐子」とも云われ、7人が朝廷と将軍家、5人が大名とその重臣、3人が一般武家と使用する人によってその人数が定められていました。
格調高い由緒ある唐子絵は、昔から平戸藩主松浦公の指定図柄とされ、他藩ではこの図柄は絶対使用することが禁じられていました。もともとは、呼んで字の如く中国からはいってきた図柄です。
唐津焼(からつやき)
佐賀県西部から長崎県にかけて焼かれた陶器。朝鮮陶工により開窯され、日本三大茶器であり茶陶(ちゃとう)が有名です。
唐津焼の名称は、元々肥前の国(佐賀県・長崎県)で焼かれ生産されていた焼き物を、唐津の港から舟で全国に出荷されてたことによる名称で、有田焼が伊万里より出荷されていたことにより伊万里と称されいたことと類似しています。
唐津市街地には古唐津の窯跡は少なく、伊万里・武雄・多久・有田・三川内など広範囲に点在していて、それぞれ地方の名にちなみ、松浦唐津・武雄唐津・平戸唐津など他にもあります。
有田焼の有田でも唐津は焼かれており、同じ窯で唐津焼と有田焼が同時に焼かれていた痕跡が残っています。
中でも十六世紀から十七世紀ごろまでの唐津焼を「古唐津」と称しています。
唐津物(からつもの)
近世、陶磁器の主産地が唐津と瀬戸であったところから、陶磁器を主に東日本では瀬戸物、西日本では唐津物と呼び慣わしてきました。
今日でも瀬戸内海沿岸、山陰、北陸から新潟県までの日本海沿岸では,焼き物のことを「唐津」または「唐津物」と称しています。
唐物(からもの)
中国から輸入されたものの総称。
焼き物では、天目・茶碗・水指・茶入・花入などで室町時代に最高評価を得ています。
河井寛次郎(かわいかんじろう)
京都五条坂に開窯。濱田庄司らと民芸運動を興し、黒褐釉、鉄絵、辰砂染、白化粧など味わいある作風が特徴。
明治23年、島根県で生を受けました。
中学の頃から陶芸の道に入ることを念とし、大正3年に京都市陶磁器試験場の技手となって釉薬、技法の研究を進めるなかで、作品展に出品するようになったのが、同10年はじめて催した個展で一躍名を知られる。
その後は柳宗悦らと民芸運動を率いる一方、制作に工夫を重ねては、華麗で斬新な秀作を次々に生み、戦後に至って大胆な上に奔放さを加えた業は、国際的な評価を受けました。
その独創性で、作品が近代陶芸における金字塔となったのは、それが同時に民族の造型そのものだったことです。
川喜田半泥子(かわきたはんでいし)
「東の魯山人、西の半泥子」とも称されました。
明治11年、大阪市の仮寓で生を受けました。
本名は久太夫政令、幼名を善太郎といいました。
生家は三重県津市の素封家で、東京・大伝馬町に寛永年間から続いた木綿問屋でした。
家業を継ぎ、百五銀行頭取など財界で活躍する一方、陶芸・書画・俳句・写真など多方面に優れた才能を発揮してきました。
とりわけ、大正初年頃から始めた作陶は、趣味の域をはるかに超え、沈滞していた陶芸界に革新的な息吹を吹き込むことになりました。
茶道に対する深い理解、作品や芸術・文化における鋭い着眼点と深い知識は、同時代に生きた陶芸家たちにも深い影響を与え昭和における陶芸復興の礎ともなりました。
皮鯨手(かわくじらで)
唐津焼に多い装飾方法の一つ。
茶碗や皿の縁に鉄釉をかけて焼くと茶褐色の発色を見ることができますが、それが鯨の肉を切ったとき、鯨の皮の黒い部分に類似しているところを連想させるところから名づけられたもので、九州地方の陶器に多く用いられます。
瀬戸唐津の茶碗の口縁は鉄釉で周囲を巻いているため皮鯨茶碗の別名があります。
絵の入った絵唐津でも同じように縁取りしたものもありますが、絵が入っている物は絵唐津と呼び、絵がない物を皮鯨と呼びます。
還元炎焼成(かんげんえんしょうせい)
焼成の際、窯の中で、酸素の少ない状態で焼成し、酸素量を減らし炭素の多い不完全燃焼で焼くことをいいます。
土や釉(うわぐすり)に含まれる金属の固有の色を発色します。
釉薬の中に含まれる金属は還元炎焼成すると鉄分の場合青色に、銅分の場合赤色に発色します。
青花や青磁、釉裏紅の釉色はこうした焼成によって得られたものです。
貫入(かんにゅう)
素地(きじ)と釉(うわぐすり)の収縮率の違いから、器面に生じたひび割れ。装飾のひとつとして使う場合もある。
貫乳ともいいます。
中国では開片と呼び、元来、宋代の官窯青磁には釉にひびの入ったものが焼成され、そのひびの入り具合を文様に見立てて、魚子紋・牛毛紋・柳葉紋・蟹爪紋・梅花片紋などと呼び、鑑賞上重要なポイントになっていました。
官窯系の青磁器にひびの入っているものが多かったところから「くわんよう」(官窯)、転訛して「くわんにゅう」となり、貫入・貫乳などの宛字が広まりました。
清朝の寧窯などでは窯出し直後、墨汁・紅柄汁などに浸して放置し、釉のひびは文様となって消えなくなります。
官窯写しの青磁器はこの方法によるものが多く見られます。
貫入が入る原因としては、焼成時のとき収縮する割合が生地(土)と釉薬(表面のガラス質)が違うので、窯の中で高温度から常温に温度が下がるときひびが入ります。
特に陶器に多く見られ、磁器の場合は生地と釉薬の成分が似ているため、収縮率の度合いが違わないためにあまり貫入は入りません。
き
喜左衛門井戸 (きざえもんいど)
「喜左衛門井戸」 一名「本多井戸」
朝鮮・李朝時代(16世紀)
大井戸茶碗・喜左衛門(きざえもん)(国宝)
京都・孤蓬(こほう)庵 口径 15.5cm
慶長の頃大阪の町人竹田喜左衛門といふ者所持しが故に名あり。
又本多能登守忠義に傳りて、本多井戸とも云ふ。
大正名器鑑より
高麗茶碗の良さというか、味わいというものは井戸茶碗に尽きるといわれています。
ということは、茶人たちが高麗茶碗に求めた美しさは、井戸茶碗のような作振りのもの、即ち飾り気のない素朴な姿、全く華美でない渋い落ち着きのある釉色、そして一つの姿として茶碗を観るとき、茫洋とした大きさと、捉えどころのない風格が感じられる茶碗ということになります。
それは正に大井戸茶碗の姿であり、「喜左衛門」はその全てを備えた茶碗といえます。
伸び伸びとしたこだわりのない姿、中央が竹の節のような高台がしっかりと受けているのが印象的ですが、その伸び伸びとしたロクロ目は、井戸茶碗の最大の特色であり、竹節状に削り出された高台も、節立っているがために、全体の姿を引き締まったものにしていることから、やはり大きな見所の一つに挙げられています。
釉は灰褐色のいわゆる井戸の枇杷色釉と呼ばれる釉薬が厚く掛かり、高台廻りは梅華皮(かいらぎ)状に縮れています。
このかいらぎはそれこそ見方によっては不潔な感じをもたせますが、全体の渋く静かな色感の中に、唯一つの激しい景色であるといえ、茶人はそうした変化に目を着けたのでしょう。
素地(きじ)
成形された焼き物の土。
焼成前は生素地、素焼後のものを素焼素地という。
岸岳窯(きしだけがま)
佐賀県東松浦郡北波多村にあり、透明の灰釉(かいゆう)を施した陶器が、初めて焼かれた唐津焼の古窯。
室町中期頃、松浦水軍によって連帰された北朝鮮陶工によって開窯されたもので、いま岸岳山腹に七つの窯跡が残っています。
窯跡出土の陶片を見ると、釉胎・器形・作調ともに朝鮮半島の初期製品に似ています。
黄瀬戸(きぜと)(きせと)
安土桃山時代に美濃で焼かれた瀬戸系の陶器。
淡黄色の釉(うわぐすり)をかけたもの。黄瀬戸は大別して二つに分けることができます。
ひとつは、釉肌が、ざらっとした手触りの柚子肌で一見油揚げを思わせる色のものを「油揚げ手」と呼び、光沢が鈍く釉薬が素地に浸透しているのが特徴です。
多くの場合、菊や桜や桐の印花が押されていたり、菖蒲、梅、秋草、大根などの線彫り文様が施されており、この作風の代表的な作品「菖蒲文輪花鉢」にちなんで「あやめ手」とも呼ばれています。
胆礬(タンパン;硫酸銅の釉で、緑色になる)、鉄釉の焦げ色のあるものが理想的とされ、とりわけ肉薄のためにタンパンの緑色が裏に抜けたものは「抜けタンパン」と呼ばれて珍重されています。
もうひとつが、明るい光沢のある黄釉で文様がないもので、「油揚げ手」に比べると、肉厚で文様のないものが多く、菊型や菊花文の小皿に優れたものが多かったことから「菊皿手」、六角形のぐい呑みが茶人に好まれたことから「ぐい呑み手」などと呼ばれています。
この手の釉には細かい貫入(釉に出る網目のようなひび)が入っています。
桃山期の黄瀬戸は、当時珍重されていた交趾(ベトナム北部や中国南部の古称)のやきものの影響が大きいと言われています。
16世紀後半から17世紀初期(天正期から慶長期初期)にかけて、大萱(現在の可児市)の窯下窯で優れた黄瀬戸が作られていたといわれ、利休好みとされている黄瀬戸の多くはここで焼かれたのではないかと考えられています。
北大路魯山人(きたおおじろさんじん)
美食倶楽部の主宰。
陶芸家で、書家。
本名房次郎。
織部(おりべ)・色絵(いろえ)などに独特の作風で料理のための器を作陶し、食器を芸術品に高めた。
明治16年3月23日、京都に生まれる。
生涯のなかで書と 陶磁器にとりわけ鬼才を発揮した彼は、専門陶工ではない趣味人ならではの当意即妙な意匠の世界に新境地を開き、北鎌倉の山崎に窯を築き、星岡窯と称した。
亀甲文(きっこうもん)
亀の甲らのような六角形を組み合わせた文様のこと。
砧青磁(きぬたせいじ)
砧青磁は中国の南宋前期時代、龍泉窯で焼かれた、やや濁りがあって青味の強い青磁釉の総称です。
龍泉窯は規模が大きく、浙江省南部の龍泉県に23カ所あり、その中には全長80mを越える龍窯もあります。
砧青磁は、厚く釉のかかった特色ある青磁で、無文、線刻、貼花など意匠で国内向け日常雑器が造られていたのと同時に、海外向けの優れた作品が、日本を始めアジアにも多く輸出されていました。
木節粘土(きぶしねんど)
花崗岩が風化して生成した粘土が木片等の有機物と一緒に流され堆積してできた不純物や鉄分を含み、低温では赤み、高温では灰色になる漂積粘土です。
外観は、灰色、褐色、暗褐色をしています。
破面が光沢を持った可塑性及び乾燥強度の高い粘土です。
木節粘土は、堆積粘土(たいせきねんど)で亜炭(あたん)等の炭化(たんか)した木のかけらを含むため木節粘土と呼ばれています。
牛篦(ぎゅうべら)牛箆(ぎゅうへら)
轆轤成型時に使う道具です。
その名の通り牛の舌の形をしています。
主に皿・碗・鉢など作るとき土を伸ばしたり、形を作ったり使い、山口県の萩焼より西部日本地区で朝鮮陶のルーツを持つ陶工達が使っています。
京焼(きょうやき)
楽焼(らくやき)は除いた、京都で焼かれたもの。
野々村仁清(ののむらにんせい)や尾形乾山(おがたけんざん)らにより、色絵陶器の優品が作られた。
金海(きんかい)
日本からの注文により朝鮮半島の慶尚南道金海地方で作られ、またこの種の茶碗の中に「金海」または「金」の文字が彫られたものがあることからこの名があります。
堅手茶碗に似て焼き締まり、また薄手で釉色は白く華やかです。
口縁が桃形や洲浜形をしたものや割高台などの形状のほか、猫掻手と呼ばれる鋭い引っかき疵が文様のようにつけられているものもあります。
金彩(きんさい)
金泥・金箔などを用いて施した華やかな装飾技法の一つ。金付、金焼付ともいいます。
金継ぎ(きんつぎ)
「金繕い(きんつくろい)」や「金直し(きんなおし)」ともいい、割れた部分を継ぎ、欠けた部分を成形し、その部分に金や銀の化粧を施し、器を修繕する技法です。
繕い後を新たな景色となす、日本独特の文化であり美学でもあります。
鈞窯(きんよう)
中国・宋代の河南省禹県を中心とした名窯。失透性の青磁釉とこれに辰砂(しんしゃ)を混ぜた紫紅釉が代表的。
この禹県を明初に鈞州といっていたことから鈞窯の名がつきました。
釉肌の青みは鉄分によるもので、釉薬に藁灰を混ぜることで珪酸が増し、失透性を帯びた一種の青磁釉と考えらています。
白濁失透釉が厚く掛かったものを月白釉、釉裏に酸化銅を施して一面に紅色を呈したものを紅紫釉、月白釉に銅呈色の不規則な紅紫の斑文があらわれたものを月白紅斑といいます。
盤・花盆のなかには極めて精巧な作りで、底裏に一、二などの数字が印されています。
元代に入ると、その作風は大胆になり色調も宋代のものに比べ濃いものが多くなっています。
金襴手(きんらんで)
色無地あるいは色絵(いろえ)や染付(そめつけ)けに金泥や金箔を用いて、文様を付けた絢爛な焼き物。
赤絵金襴とも呼ばれます。
く
櫛目(くしめ)
装飾技法の一つ。
櫛の歯がついたヘラなどで施した文様のこと。
櫛目高台(くしめこうだい)
鍋島焼の皿の高台側面に、染付(そめつけ)で櫛目状に施された文様。
藩窯(はんよう)の製品である証となっています。
九谷焼(くたにやき)九谷(くたに)古九谷(こくたに)
金沢市から小松市周辺で焼かれている磁器。
京焼(きょうやき)の色絵(いろえ)の流れと、緑・黄・紫を基調とする古九谷様式(こくたにようしき)の流れが主流。
九谷焼の発祥は、今からおよそ340年前の明暦年間(1655~57)にさかのぼります。
加賀藩の支藩大聖寺藩の殖産興業の一環として領内の鉱山開発に着手した初代藩主前田利治が、江沼郡九谷村の金山で磁鉱が発見されたことを知り、金山の錬金術師だった後藤才次郎に色絵磁器を焼くことを命じたのが始まりといわれています。
才次郎は、当時すでに磁器の産地として知られていた肥前(佐賀県)におもむき、酒井田柿右衛門によって完成された赤絵の技術を習得しました。
そして有田の工人を連れて帰国するとただちに九谷に窯を築き、加賀の工人田村権左右衛門らを指導して色絵磁器製造に着手したのです。
口紅(くちべに)
皿や鉢などの口縁に鉄を塗ったもの、縁紅(ふちべに)ともいう。
縁が割れやすいための補強用として塗られていました。
唐津では皮鯨といいます。
沓形(くつがた)沓茶碗(くつちゃわん)
瀬戸黒(せとぐろ)、織部(おりべ)、唐津(からつ)など不規則な楕円形をした茶碗などをいいます。
口作りは玉縁で不規則な楕円形をなし、下部にくびれがある鉢や茶碗などをいう。名称はその姿によるもの。御所丸・織部・志野の沓茶碗や唐津の沓鉢はその典型となっています。
うつわの口辺を成形後に押さえ、日本古来の木沓(ぐつ)を連想させる形にした
切立よりも上部が狭まった形で、口は不規則な楕円形をなすものが多く茶碗・鉢・向付などに多く見られます。
御所丸・織部・志野の沓茶碗等は人工的な歪みが主だが、唐津の場合元々は真円の器が多く、それが焼く時の高温などで楕円にひずんだ自然的な沓形が多く見られますが、美濃地方の織部の影響を受けた後の沓形は楕円や歪んだのを重要視して、その目的で作ったのが多くなっています。
それは、織部の沓茶碗と唐津の沓茶碗とを比較すると良く分かります。
国焼(くにやき)
瀬戸(せと)と京都以外で焼かれた茶器。近年は日本のやきものの総称として、また地方窯という意味で使用。
くらわんか茶碗(くらわんかぢゃわん)
江戸時代に淀川で船に酒食を売る商人たちが使った、厚手の染付茶碗(そめつけ)で波佐見(はさみ)・三川内(みかわうち)・砥部焼(とべやき)などの産地の茶碗のことを指します。
使い捨ての器と呼んで言う程の雑器だが、それ故風格があり、胎土もぶ厚くて手取りがずっしりと重く、絵柄も素朴です。
製作年代は江戸時代の中期から後期に掛けての頃が一番盛んした。
一般に文化文政時代の作品であると考えられる。大阪淀川に船を浮かべた一膳めし屋がこの茶碗に雑炊を盛り、行き来する旅人に「めしくわらんか」と呼びかけたことに由来しています。
黒織部(くろおりべ)
織部の一種で、形を歪ませた茶碗に、黒釉が掛け分けられています。
白い部分は白釉が掛けられ、鉄絵の具で桝形や菱形などが描かれています。
黒唐津(くろがらつ)
鉄分の多い釉(うわぐすり)のため、飴色・黒褐色・淡黒になった唐津焼をいいます。
木灰と鉄の含有量が多い岩石とを混ぜ合わせた釉薬をかけ焼成したもので、鉄分の含有量の量や、原料の成分により、黒、飴、柿色などに変化します。
装飾的には拘らない甕や壺などの民具に多く使われています。
黒唐津は、茶碗・壺・水指・花入などがあり、ほとんどの諸窯で焼成されていました。
蛇蝎唐津は黒唐津の一種で、黒釉の上に失透性の長石釉をかけて焼成したもので、釉肌が、蛇やトカゲの肌に似ているところからその名があります。
黒薩摩(くろさつま)
黒物「くろもん」とも呼ばれ、薩摩焼の中でも、黒釉(こくゆう)をかけたものをいいます。
黒楽(くろらく)
引出黒の一種で、楽焼(らくやき)の中で黒色のものをいいます。
低火度(ていかど)焼成ですが赤楽(あからく)よりは火度は高く焼成されています。
小型の窯でフイゴをつけて炭火で焼き、窯から引き出してすぐに水に浸し、黒の色調と楽焼のもつ柔らかさを出しています。
け
珪石(けいせき)
石英を主体とする地核の30%を占める珪酸質の岩石。陶磁器や釉薬(ゆうやく)の原料として利用。
珪酸(けいさん)
釉(うわぐすり)の主原料で、溶けて冷却するとガラス質になるが、単独では溶けにくい。
景徳鎮(けいとくちん)
唐時代に始まり、白磁青磁、青白磁(せいはくじ)、染付(そめつけ)、赤絵(あかえ)など様々な技法のものを焼いた中国江南省にある大窯業地。
景徳鎮窯では明時代中期になると民窯を中心にしだいに五彩、すなわち釉上彩の技法が盛んになっていきました。
鶏龍山(けいりゅうざん)
朝鮮・李朝時代初期の15,6世紀の窯。忠清南道に位置し、三島(みしま)・刷毛目(はけめ)・白磁(はくじ)などを焼いた。
鉄絵粉青を俗に鶏龍山(けいりゅうざん)と呼びますが、これは窯が忠清南道公州郡反浦面の鶏龍山山麓、鶴峰里に位置するためこの名があります。
鶏龍山窯址は、韓国で初めて発掘調査がおこなわれた窯としても有名です。
その成果は1929年、神田惣蔵・野守健編『鶏龍山麓陶窯址調査報告』(朝鮮総督府)にまとめられています。
発掘調査の結果、6箇所の窯が確認されたほか、数多くの印花や粉青鉄絵の陶片が出土しました。
また、「成化(せいか)二十三年」(1487年)や「嘉靖(かせい)十五年」(1536年)銘の墓誌などが出土し、粉青の年代を考えるうえで貴重な資料となりました。
この鶏龍山発掘の結果は広く受け入れられ、新たな高麗茶碗のひとつとして、あるいは唐津の源流説ともなっています。
景色(けしき)
器の表目に現れた、窯変(ようへん)や流し掛けなどによる釉薬(ゆうやく)や形の変化で、品物を鑑賞する場合の見所の一つになります。
景色は二通りあって、高麗茶碗などの磁肌に現れてくる景色は、使い込むのしたがって出てくる「雨漏り」などの育つ景色であり、自然釉は窯の中でつくられる作品そのものの景色です。
化粧掛け(けしょうがけ)
素地(きじ)とは違った色に仕上げるために、目指す色の陶土を表面に薄く掛けること。
化粧掛けは、素地が黒っぽいものや肌が美しくないものを白く見せるために行われていました。
表面に白い土の層をつくることによって、素地は白く滑らかになり、またその上に文様を描くにしても色がきれいに見えます。
こうした化粧掛けの技法は古くからあり、たとえば中国においては、唐代の三彩、宋代の磁州窯の製品等によく見られます。
磁州窯の場合は、化粧掛けされたものの上に文様を描くほか、文様の部分だけ表面の化粧土を掻き落とし、素地そのものの灰地を文様として表出させています。
朝鮮では化粧土を用いた装飾は多く、象嵌や刷毛目とともに、化粧掛けによる「粉引き(こひきまたは粉吹き)」の茶碗が名品として残されています。
粉引きの場合は、泥漿に浸す方の化粧掛けで、日本では九州各地の陶器窯でみられる他、美濃の織部や京都の乾山にも見られます。
特に、乾山は化粧土を絵具として用いていたようです。
下手もの(げてもの)
美術工芸品ではなく、日用雑器の類。民芸運動により素朴な美しさが評価。
蹴ろくろ(けろくろ)
足を使い、蹴って(足で引く場合もある)回転させる轆轤のこと。
作陶するときに使う道具で、九州・山口県の地区はルーツは朝鮮半島によるのが多く轆轤を足で蹴りながら作陶していました。
美濃瀬戸地区は主に手で回す「手回し轆轤」で作陶しています。
建盞(けんさん) 建盞天目(けんさんてんもく)
中国・宋時代に建窯でつくられた天目茶碗の総称。
口縁がひねり返し、高台は小さい。
中国福建省にある建窯で造られていた天目茶碗には、口縁部が強く反るタイプのものと、あまり反らないタイプ(いわゆる天目形)の2種類があります。
建窯の天目茶碗にかけられた黒い釉薬には、茶色や銀色の細かい縦筋が無数に見られるものが多く、日本では、これを稲の穂先の芒(禾)に見立てるため、この種の釉薬がかかった天目茶碗を禾目天目と呼んでいます。
建水(けんすい)
茶碗を清めた湯や水を入れるもので「こぼし」ともいいます。
唐銅、砂張(さはり)、 陶磁器、木地物などがあります。
建窯(けんよう)
中国・福建省建陽県にあった宋・元代の名窯。
黒釉(こくゆう)のかかった天目茶碗(てんもくちゃわん)を焼き、鎌倉・室町時代に日本へ輸出していました。
唐時代より青磁を、また宋時代から元時代には、黒釉の掛かった建盞と呼ばれる天目茶碗を産した。天目に用いられる黒釉は鉄分を多く含むために窯変が起こり、禾目天目・油滴天目・曜変天目がうまれた。明代に入ると牙白釉の掛かった白磁もつくるようになりました。
献上伊万里(けんじょういまり)
有田の磁器のうち、宮中の献上品。
献上唐津(けんじょうがらつ)
唐津市唐人町の御用窯(ごようがま)で江戸時代後期に焼かれた、肥前唐津城主より徳川将軍家に献上した精緻な唐津焼の茶碗。
唐津城主詩寺沢志摩の守広高が、寛永年間(1854-44)椎の峰の工人に命じてつくらせたのにはじまり、歴代の唐津城主が献上した。
中でも安政年間(1854-60)小笹原候により献上された雲鶴象嵌の茶碗が有名。
宝永4年から坊主町・唐人町で作られるようになり、大正期まで焼成されていた。
こ
古伊万里(こいまり)
明治以前に作られた伊万里焼で、特に赤絵(あかえ)が完成して以降のものをいう。それ以前のものは初期伊万里と呼びます。
「古伊万里」(こいまり)とはその名のとおり古い伊万里焼のことをさし、通常は江戸時代の伊万里焼を称しています。
染付(そめつけ)の藍色の素地に、上絵の金、赤、緑、黄色などで装飾した作品を「古伊万里様式」と呼んでいますが、藍色と金、赤の組み合わせが基本で、金欄手(きんらんで)の古伊万里と呼ばれることもあります。
「古伊万里様式」は、それまで流行していた「柿右衛門様式」に替わり、元禄期(1688~1704)に生まれています。
「柿右衛門様式」同様にヨーロッパで好まれ、元禄から享保(1716~1736)にかけて大量に輸出されました。
余白がないほど文様が描きこまれた絢爛豪華な作品もあり、豊かな時代の元禄時代を反映しています。
構図の特徴は、器を放射状の直線や唐花(からはな)状の曲線で区別し、窓絵(まどえ)と地文様(ぢもんよう)を交互に描きます。
文様には唐花文(からはなもん)、獅子牡丹文(ししぼたんもん)などがあります。
口縁(こうえん)
蓋がついていない器の、一番上にあたる縁の部分の周辺のこと。
香合(こうごう)
香を入れるために使う、蓋付きの小さい器で茶道具のひとつ。
口唇(こうしん)
器の一番上のへりにあたる部分のこと。
高台(こうだい)
糸底(いとぞこ)ともいいます。器を安定させるために底につくられた台。
同じ土で後からつける付け高台と、削り高台の2種の技法があります。
唐津焼の高台の種類について、
唐津焼の高台には作為の有る・無しに問わずいろんな種類がありますが、
そんな高台を先人たちは色々な名称で楽しみ鑑賞してきました。
竹節高台(たけふしこうだい)
二重高台(ニジュウコウダイ)
三日月高台(ミカヅキコウダイ)
藁敷き高台(ワラシキコウダイ)
貝高台(カイコウダイ)
貝殻高台(カイガラコウダイ)
竹節高台「たけふしこうだい」
略して竹の節とも言う。
茶碗の高台が竹の節状になったものを言う。
井戸茶碗の約束の一つになっているが、その他の朝鮮茶碗や唐津茶碗の特色でもあり、茶碗の一景色とされる。
二重高台(ニジュウコウダイ)
輪形につくられた高台の畳付の面に、さらに一筋の溝を彫ったもの。
志野焼・唐津焼などに見られます。
三日月高台(ミカヅキコウダイ)
高台畳付の幅が均等にならず幅が狭い所があったり広い所があったりちょうど月の形「三日月」に見立てて、何時の時かそう呼ぶようにらしい。
昔の技術が下手だった訳ではなく、蹴り轆轤のすわりが悪かったり芯がずれたりした為と思われます。
今では許され難いことでも昔の茶人は洒落で心地よい名前を付けたり、それでも良しという作り手のおおらかな時代に惹かれますね。
高台敷き高台(ワラシキコウダイ)
備前焼の火襷と類似しています。
焼く工程で他の器物と溶着しないよう器物の間に藁を敷いて焼くが、その藁の跡が付いたものを言います。
又、藁の代わりに籾殻を強いて焼くときは籾殼高台といいます。
付け高台(つけこうだい)
高台を、ロクロの上で削り出すのではなく、あとから粘土でつくった紐を輪にして貼りつけたものをいいます。
交趾焼(こうちやき)
中国明時代後期から清時代初期に作られた三彩陶。
交趾(こうち)(現在のベトナムの北部)の産と考えられたことが名前の由来です。
高麗(こうらい)高麗青磁(こうらいせいじ)高麗茶碗(こうらいぢゃわん)
朝鮮半島の高麗時代(918~1392年)につくられた陶磁器の総称。
高麗王朝期に生み出された青磁。
高麗青磁は宋朝の影響を受けてはいるが、下地に美しい彫刻をし、そこに独特の白土や黒土の象嵌をして模様を浮かび上がらせているのが特徴です。
高麗王朝は1392年に滅んで李朝の時代になるましたが、当時は李朝時代も異名として使っていました。
茶道における高麗茶碗はほとんどが李朝時代のものであり、高麗時代のものはほとんどありません。
井戸・割高台・呉器・半使・絵高麗・刷毛目・伊羅保・高麗青磁・三島・粉引・たまご手・堅手・金海・熊川(こもがい)・御本・柿の蔕(へた)・ととやなどに分類されます。
香蘭社(こうらんしゃ)
明治7年に設立された有田の磁器工場。輸出向けの大量生産を目指し、現在も有田の主要工場。
呉器(ごき)
李朝(りちょう)時代に作られ、見込が深く高台と丈の高い高麗茶碗の一種。。
御器・五器とも書く。
呉器の名は、形が椀形で禅院で用いる飲食用の木椀の御器に似ているためといわれる。
一般に大振りで丈が高く見込みが深く、高台は外に開いた「撥高台(ばちこうだい)」が特色とされる。
素地は堅く白茶色で、薄青みがかった半透明の白釉がかかる。
「大徳寺(だいとくじ)呉器」「紅葉(もみじ)呉器」「錐(きり)呉器」「番匠(ばんしょう)呉器」「尼(あま)呉器」などがある。
「大徳寺呉器」は、室町時代に来日した朝鮮の使臣が大徳寺を宿舎とし帰国の折置いていったものを本歌とし、その同類を言う。
形は大振りで、風格があり、高台はあまり高くないが、胴は伸びやかで雄大。
口辺は端反っていない。
古清水(こきよみず)
京焼の一種で、野々村仁清以後奥田穎川(おくだえいせん:1753~1811)以前のもので、仁清の作風に影響されて粟田口、八坂、清水、音羽などの東山山麓や洛北御菩薩池の各窯京焼諸窯が「写しもの」を主流とする茶器製造から「色絵もの」へと転換し、奥田穎川によって磁器が焼造され青花(染付)磁器や五彩(色絵)磁器が京焼の主流となっていく江戸後期頃までの無銘の色絵陶器を総称します。
幕末に五条坂・清水地域が陶磁器の主流生産地となり、この地域のやきものを「清水焼」と呼び始め、それ以前の色絵ばかりでなく染付・銹絵・焼締陶を含む磁器誕生以前の京焼を指して「古清水」の名が使われる場合もあります。
古九谷様式(こくたにようしき)
伊万里焼(いまりやき)の中の様式の一つ。作風は五彩手・青手・南京手の三つに大別。
黒釉(こくゆう)
黒色に発色する高火度釉。中国では漢代の越州窯(えっしゅうよう)ではじまり、日本では古瀬戸からはじまった。
五彩(ごさい)
白磁や白釉陶に、赤・緑・黄・紫・青などの明るい上絵具で文様を描いた中国の色絵(いろえ)。
呉須(ごす)
酸化コバルトを主成分し染付(そめつけ)に用いる彩料。釉(うわぐすり)をかけ焼成すると藍青色になり、鉄釉(てつぐすり)に加え上絵具(うわえのぐ)の青としても用います。
中国では青料といいます。
還元焔により藍色を呈し、酸化させると黒味を帯びます。
コバルト鉱が風化して水に溶けて沈殿し、鉄、マンガン、ニッケルなどの化合物が自然混合した天然のコバルト混合土。
これらの化合物が多いほど黒くなる。
日本では産地の浙江省紹興地方が古くは呉の国と呼ばれたため呉州(ごす)と呼び呉須と書いたとされます。
元朝(1279~1368)末に、西域よりスマルト(酸化コバルトを4~6%溶かし込んだ濃紺色のガラス)、中国で「蘇麻離青(そまりせい)」と呼ばれる鮮やかな青藍色を発する青料が招来し、景徳鎮で使われたが、明朝成化年間(1465~87)に輸入が途絶え「土青(どせい)」といわれる中国産の黒ずんだ青料が使われるようになりました。
明朝正徳年間(1506~21)からは、西アジアより「回青(かいせい)」と呼ばれる、明るい青藍色のものが輸入され、嘉靖(1522~66)、隆慶(1567~72)、萬暦(1573~1619)の青花に主として使われるようになりました。
呉須赤絵(ごすあかえ)
赤や緑を主に鮮やかな色で、奔放な花鳥文、魚文などが描かれた中国明代の後期に焼かれた色絵磁器。
赤・青・緑に、黒の線描きが加えられているのが特徴。
茶人に好まれ、桃山時代から江戸時代初期に大量に輸入されました。
御所丸(ごしょまる)
高麗茶碗の一種。
御所丸の名は、朝鮮との交易に使われた御用船を御所丸船といい、文禄・慶長の役のとき、島津義弘がこの手の茶碗を朝鮮で焼かせ御所丸船に託して秀吉に献上したことからきたと思われます。
桃山より江戸期にかけ日本から朝鮮に御手本(切形)を送って焼かせたものを御本といい、古田織部の御本で金海の窯で焼かせたもので「古田高麗」ともいい、御本としては最も古いものになります。
堅手の一種で「金海御所丸」ともいいます。
形は織部好みの沓形で、厚手。
腰には亀甲箆という箆削りがあり、高台は大きく、箆で五角ないし六角に切られています。
高台は釉がかからず土見せ。
白無地の「本手」(白手)と、黒い鉄釉を片身替わりに刷毛で塗った「黒刷毛」と呼ばれるものがあります。
古瀬戸(こせと)
瀬戸で生産された陶器のうち、鎌倉時代の初めから室町時代の中頃までの施釉陶器(せゆうとうき)を古瀬戸と呼びます。
従来、その起源は陶祖加藤四郎左衛門景正(通称藤四郎)による中国製陶法の招来とされています。
道元禅師が貞応2年(1222)、明全に従って宋に渡ったとき藤四郎が道元の従者として渡宋し、禅修業の傍ら逝江省の瓶窯鎮で製陶の修業をし、安貞2年(1228)帰国後、尾張の瀬戸に窯を築き、中国風の陶器を焼いたのが始まりと伝えられています。
近来は桃山時代以前の瀬戸陶磁器を古瀬戸と概称する場合があります。
「灰釉(かいゆう)」のみが使用された前期(12世紀末~13世紀後葉)、「鉄釉(てつゆう)」が開発され、素地土の柔らかいうちに印を押して陰文を施す「印花(いんか)」、文様をヘラや釘、クシ等で彫り付ける「画花(かっか)」、粘土を器体に貼り付けて飾りにする「貼花(ちょうか)」など文様の最盛期である中期(13世紀末~14世紀中葉)、文様がすたれ日用品の量産期となる後期(14世紀後葉~15世紀後葉)の三時期に区分されています。
前期の「灰釉(はいぐすり)」は、朽葉色の釉薬で戦前一般には「椿手(ちんしゅ)」と呼ばれました。
鎌倉後期以降の「鉄釉」は鬼板という天然の酸化鉄を釉薬に混ぜたもので、黒若しくは黒褐色に発色します。
今日、この黄釉若しくは黒釉の掛かったものも古瀬戸と称することがあります。
古染付(こそめつけ)
古染付とは必ずしも古渡りであることを要せず、今日では明末期に景徳鎮の民窯で特に日本向けに作られたと思われる独特の風趣のある器形や文様をいいます。
口縁部や稜線部などに「虫喰い」とよぶ釉はげが見られ、茶人には大いに好まれ日本に多く残存している。
民窯ならではの大らかさと独特の風雅な趣が見られます。
木葉天目(このはてんもく)
木葉天目は、中国江西省の吉州窯で焼かれた玳玻盞天目の一種で、黒釉面に実際の木の葉を貼り付け焼成されたものです。
この碗は、見込み中央から口縁にかけて木の葉の姿が茶褐色に発色して現れ、焼け縮みの多い部分は虫喰い状に欠失しています。
高台は吉州窯特有の黄白色の素地が見れます。
伝来は不詳となっています。
コバルト(こばると)
下絵具として使用される青色の発色剤。19世紀以降ヨーロッパから輸入され、現代食器に多用。
粉引(こびき・こひき)
粉吹(コフキ)ともいい、李朝期の朝鮮茶碗の一種。土・釉から慶尚南道産の三島刷毛目の類と考えられる。鉄分の多い土であるため、白尼を一面に化粧掛けしているが、その白尼の粒子がやや荒いため、さながら粉をまぶしたような肌に見えるのでこの名があります。
元来は、鉄分の多い土は焼くと黒くなりますが、白く見せるために胎土の上に白土を使って化粧する技術です。
粉引の場合は全体にかける為に化粧土を水に溶かした溶液の中に漬け込む方法か、柄杓で流し掛けする方法を行います。
窓見せとは、化粧土か釉薬がかかっていない部分を作る装飾技法の一つです。自然にできる場合と意図的に作る場合があります。
御本(ごほん)
「御本(ごほん)」とは、手本をもって作られたという意味です。
土の中に含まれている鉄分が窯(ようへん)変し、赤い色彩や斑点状の模様が現れること。
熊川(こもがい)
見込(みこみ)が深く、腹がゆったりとした丸みを帯び口縁はわずかに端反った高麗茶碗(こうらいぢゃわん)の一種。
熊川の名は、慶尚南道の熊川という港から出たもので、その近くの窯で出来たものが熊川から積み出されたためこの名があります。
「熊川なり」という形に特徴があり、深めで、口べりが端反り、胴は丸く張り、高台は竹の節で比較的大きめ、高台内は丸削りで、すそから下に釉薬がかからない土見せが多く見られます。
見込みの中心には「鏡」「鏡落ち」または「輪(わ)」と呼ぶ小さな茶溜りがつくのが一般的です。
また釉肌に「雨漏り」が出たものもあります。
「真熊川(まこもがい)」「鬼熊川(おにこもがい)」「紫熊川(むらさきこもがい)」などの種類があり、「真熊川」は、作風は端正でやや深め、高台も高く、素地が白めのこまかい土で、釉は薄い枇杷色、柔らかく滑らかで細かい貫入があります。
古人は咸鏡道(かんきょうどう)の熊川の産と伝えて、真熊川のなかで特に上手のものを、その和音を訛って「かがんどう(河澗道・咸鏡道)」とか「かがんと手」と呼でいました。
「鬼熊川」は、真熊川にくらべ下手(げて)で、荒い感じがあるのでこの名があります。
形はやや浅めで高台が低く、見込みは広いものが多く、鏡が無いものもあります。
時代は真熊川より下るとされています。
「紫熊川」は、素地が赤土で釉肌が紫がかって見えるものを指します。
御用窯(ごようがま)
藩窯(はんよう)のことで、江戸時代に藩が殖産や専用の製品を作らせるために開いた窯。