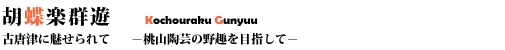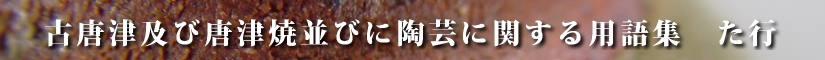古唐津及び唐津焼並びに陶芸に関する用語集 た行
た
高取焼(たかとりやき)
福岡県朝倉郡で、朝鮮陶工八山(やさん)が開窯。朝鮮の影響が残る古高取、遠州(えんしゅう)の指導による遠州高取(えんしゅうたかとり)など茶器が有名。
高取焼は元々、福岡県直方市にある鷹取山の麓にて焼かれており、朝鮮出兵の際に陶工、八山(八蔵重貞)を連れ帰って焼かせたのが始まり。
窯場には永満寺窯、内ヶ磯(うちがそ)窯、山田窯があり、これらを「古高取」と呼んでいます。
江戸時代には黒田藩の御用窯として繁栄、元和年間には唐津からの陶工を招き、技術を向上させています。
そして寛永年間に入ると、二代目藩主黒田忠之は親交の深い小堀遠州と交流を深め、遠州好みの茶器を多く焼かせました。
それが縁で、遠州七窯の一つに数えられ、茶陶産地として名を高めることとなった。
この頃の中心は白旗山窯で、遠州好みの瀟洒な茶器は「遠州高取」と呼ばれた。
その後は小石原に移り(小石原高取)、より繊細な作品が多く焼かれました。
以後は、福岡の大鋸谷に移転(御庭高取)、18世紀には「東皿山」と「西皿山」に分けられ、細分化されていった。
今日では数カ所の窯元が至る所に残っており、廃窯した窯場にも再び火が灯り再興しています。
武野紹鴎(たけのじょうおう)
武野紹鴎は堺の町衆です。
通称は新五郎、名は仲材、大黒庵と号しました。
堺では屋号を皮屋といい、おそらく武具甲冑などに関係する商家であったと思われます。
武野家は堺では最も富裕な家でしたが、紹鴎は若き日に京都にのぼり連歌に没頭しました。
当時、歌学の権威であった三条西実隆について古典を勉強し、『詠歌大概』を授けられました。
おそらくこうした連歌の素養が、紹鴎の茶の湯に大きな影響を与えたと思われます。
堺に戻ってからは、南宗寺に住した禅僧大林宗套に参禅し、茶の湯に開眼すると同時に茶禅一味のわび茶を深めることができました。
紹鴎は名物といわれる道具を60種も所有する一方、白木の釣瓶を水指に見立てたり、竹を削って自ら茶杓をつくったり、あるいは青竹を切って蓋置にするなど、清浄な白木の美を茶の湯に加えることに成功しました。
こうした創造的な茶の見方が紹鴎の弟子千利休に伝えられ、茶の湯は大成されることになります。
叩き(たたき)叩き作り(たたきづくり)板起こし(いたおこし)
内側に当て具をして、外側から叩き締める成形法で、唐津独特の伝統技法。
古くは紀元前より中国で生産され、日本には朝鮮半島を経て伝わり、様々な変化を遂げ須恵器となり日本各地に伝わり生産されるようになりました。
須恵器と唐津の叩との関係は定かでありませんが、朝鮮半島には新羅のころの焼き物があるがそれと古唐津の叩壺なんかはよく似ています。
室町末期より桃山期では日本の各地ではあまり見受けられませんので、これより判断するには、この叩技法は、唐津へ朝鮮半島より轆轤(ロクロ、円盤状の上で焼き物の生地を成形する道具)の上での水引きをする轆轤成形技法と供に伝わってきたと推測されています。
今日でも東南アジア周辺や世界各地でもこの技法により生産されています。
その特徴は見た目より軽く、瓶・壺・水指・花入・徳利など袋状になった形の生地を成形するときに使われている技法で、その意味合いとして、穀物を入れたり、水・油・塩など入れたりして持ち運びするときに器自体が重いより軽い方が適したと考えらています。
当然、水引きの轆轤成形した物よりも叩成形した方が薄く軽く仕上がります。
叩成型法とは、轆轤の上に底の部分となる板を作りその上から紐状の撚り土を積み上げていく紐作り技法で円筒を作り、外側に木製の叩板で内側に丸太のしんで作ったあて木をあて外側より叩ながら、土を締め薄くのばし成形をする(叩かずにそのまま水引きをするという板おこし技法もある)。
内側には丸太の年輪の跡が付き青海波状紋(セイカイハジョウモン・上左端画像)という名前まで残っています。
古唐津の初期の頃は瓶や壺などが主だったが、お茶の文化が入ってくるとその軽さ故、塩壺などを水指にと見立てたり、水指や花入も生産され今日に引き継がれています。
板起こし(いたおこし)
叩技法とほぼ同じだが、最後の工程で叩きをせずに水引きによる整形が特徴で、内側の青海波状紋の有無で判断しないと解らないくらい似ています。
唐津以外の窯での甕・壺等の制作はこの技法でなされてるようです。
畳付(たたみつき)
茶入や水指の底の畳に当あてたる部分を指す。
盆付とも呼ぶ。
現在は、器物の底の部分の総称になっています。
たたら造り(たたらづくり)
「たたら」という、陶土を板状にしたものを、目的に合わせて切ったり、つけだしたりして成形する方法。
日本古来の製鉄法を『たたら』と言うのと全く違い、陶芸のタタラとは板状の粘土のことや、陶土を板状や帯状にしてから成型したものをいいます。
立杭焼(たちくいやき)
兵庫県多紀郡今田町の上・下立杭は、丹波焼(たんばやき)の中心地であるため、丹波焼(たんばやき)の代名詞。
濃(だみ)
染付(そめつけ)の輪郭線の中を、専用の太い濃筆むらなく綺麗に塗りつぶす、下絵付けの技法。
塗ることを有田では濃みという。
下絵の染付の濃みと、上絵の色絵の濃みがある。
有田では、染付の濃み筆は太い特有の筆を昔から使っています。
丹波焼(たんばやき)
兵庫県今田町で中世から続く陶器。中世は自然釉(しぜんゆう)の掛かった壺や鉢、桃山時代後期から江戸時代には施釉(せゆう)の陶器。
胆礬(たんばん)
硫酸第二銅で、緑色の釉や赤い釉の呈色剤。または、黄瀬戸(きぜと)に施された緑の斑点。
ち
茶入(ちゃいれ)
点前に使用するための、濃茶を入れる陶製の容器(小壷)。
通常は、象牙製の蓋をし、仕服(しふく)を着せます。
薄茶の容器のことは薄茶器、茶器という。
京都建仁寺の開山栄西禅師が宋から帰朝した際に、洛西栂尾の明恵上人に茶の種を贈るのに用いた漢柿蔕(あやのかきべた)の茶壷が始まりといわれます。
元々は薬味入・香料入などに使用されていた容器を転用したもです。
到来物の茶壷を唐物(からもの)茶入または漢作唐物茶入と称し、肩の張った物を「肩衝(かたつき)」、林檎に似た形の「文琳(ぶんりん)」、茄子に似た形の「茄子(なす)」、文琳と茄子の合の子のような「文茄(ぶんな)」「鶴首(つるくび)」「丸壺(まるつぼ)」「大海(たいかい)」「尻膨(しりぶくら)」などその姿から名付けられ分類されています。
その後、日本でつくられた茶入を和物茶入と称し、瀬戸の加藤四郎左衛門景正こと、藤四郎を陶祖として瀬戸窯を本窯と称し、四代目の破風窯までを個別に扱い五つに分類されています。
加藤四郎左衛門が瓶子窯で焼いたものを「古瀬戸」または彼の法号をとり「春慶」と称し、二代が焼いたものを藤四郎窯、真中古(まちゅうこ)という。
三代目が焼いたとされる金華山窯、四代目が焼いたとされる破風窯を中古物と称する。
利休の頃の破風窯以後の瀬戸、美濃、京都などで焼かれたものを後窯(のちがま)と称する。
その他は国焼(くにやき)の名称のもとで、各々その産地を冠して呼び名としています。
茶壺(ちゃつぼ)
石臼で擂りつぶす前の抹茶、すなわち碾茶(葉茶)を保管するために用いられる陶器製の壺(葉茶壺)です。
古くは抹茶を入れる茶入を小壺と呼んだことに対して大壺とも称された。
茶家(ちゃか)
薩摩焼(さつまやき)の酒器で、高さが低く平らな器形。
茶陶(ちゃとう)
茶の湯に用いられる焼き物のこと。茶壺(ちゃつぼ)、茶入(ちゃいれ)、建水(けんすい)など喫茶に関わるものから懐石の道具、炭道具など多彩。
貼花(ちょうか)
胎土と同じ土で、草花などの文様を作り、これを貼付けて釉(うわぐすり)をかけた貼付文様のこと。
素地に文様を貼付ける技法で、貼花(ちょうか)ともいいます。
型からぬいた文様を貼付けることが多いが、紐状の粘土を貼付けて文様を作るやり方もある。レリーフ状の陽刻文様を器に施す場合、ロクロで器を成形した後、素地の上に貼付ける方法と、器の表面を彫り込み、文様を浮彫にする方法、さらに文様そのものを彫り込んだ型を用いて、器胎を成形すると同時に陽刻文様を施す方法の3通りがある。
貼付けの技法は、古くは6世紀の中国の青磁や緑釉の作品にこの技法がみられ、7世紀の唐時代の三彩には盛んに用いられている。日本ではあまり発達しなかったが、17世紀以降の各地の窯で時々用いられている。ヨーロッパにおいては、18世紀のドイツの塩釉によるストーンウェアやイギリスのウェッジウッドなどに、精巧な型抜きの貼付け技法がみられる。
九州の陶磁器の中では、17世紀前半の三股(みつのまた)青磁(長崎県)や18世紀の鍋島青磁(佐賀県)に優れた貼付けの作品がある。
佐賀県立九州陶磁文化館報 セラミック九州/No22号より(平成2年発行)
長次郎(ちょうじろう)
楽茶碗は千利休の創意により、長次郎が作り始めたものです。
長次郎の茶碗は数多く伝世しているがその作行きは同じではありません。
この黒茶碗は姿の整った半筒形で、手びねりで作られ、見込みのかせた釉調に対し、外側には光沢が残っています。
添状には「大黒」と同寸であることが記されています。
端正な姿は「大黒」と共通するところであるが、張りの強い腰ややや幅広の高台畳付(挿図)からすると、初期の頃からやや降った時期の作と思われます。
長石釉(ちょうせきゆう)
長石を主成分とした釉薬(ゆうやく)で、やわらかな白色を発色。志野(しの)は代表的。
朝鮮唐津(ちょうせんからつ)
唐津焼の一種で、天正から寛永(1573-1644)年代の所産とされ、藤ノ川内窯・鬼子嶽帆柱窯・鬼子嶽皿屋窯・道納屋谷窯・金石原広谷窯・大川原窯などで焼成されていました。
海鼠釉と黒飴釉を掛け分けにしたもので、土質は赤黒です。
水指・花入・皿・鉢などが多く、茶碗は稀です。
唐津の窯で焼かれたことと、作風が朝鮮中部の諸窯で焼かれたものの流れを汲むところからの名称と称であろう。
茶道辞典淡交社より
朝鮮唐津とは絵唐津・斑唐津など、代表的な唐津の装飾の一つで、黒飴釉の上に海鼠釉を掛けたりまたその逆海鼠釉の上に黒飴釉を掛けたりしたものです。
この技法は全国の諸窯などに数多くありますが、朝鮮唐津は、黒飴釉の部分と海鼠釉の部分とを別々に掛け分けて、やや重なり合った部分が高温でガラス化し黒の部分と白の部分が溶け合い、絶妙な色と流れ具合の変化が特徴になります。
その名称の由来として、一説によりますと当時外国と言えば朝鮮が一番身近のようで、外国と言えば朝鮮という意味合いから来て、異国の所産のような唐津焼、朝鮮唐津と伝えるようになったようです。
でも朝鮮半島には朝鮮唐津のルーツになるような品々は少なく、日本に渡ってきてから発展したと解釈した方が良いと思います。
唐津焼は、初期の頃は壺・皿・碗等の一般民衆が使う器を生産していたのですが、桃山時代の豊臣秀吉の朝鮮出兵(1592)頃より秀吉をはじめ千利休・古田織部等の中央の武人茶人達の影響を受け、お茶の文化が入ってき来たようです。
そのような時代的な背景で形状や装飾等に変化が現れてきたように思われます。
装飾の面では、初期の唐津には単独の顔料で絵を描き一種類の釉薬を掛けているだけが多かったのですが、時がたつにつれ絵唐津や青唐津などもそうですが、朝鮮唐津は特に、織部焼がペルシャの陶器に影響を受けたように唐津もそのようで、それぞれ違う釉薬を使い分けた装飾法が発展したと思います。
今でこそ流れ具合を重要視しますが、昔は、ただ掛け分けたという感じが強いようです。
作品には水指、花入、徳利、茶碗、皿などがあり藤の川内窯で開かれたものが多くあります。
中世六古窯(ちゅうせいろっこよう)六古窯(ろっこよう)
日本六古窯は中世六古窯のことで、最近の研究では中世二十数窯とも言われ、その数は増えていますが、日本六古窯は中世の代表的な窯で信楽、備前、 丹波、越前、瀬戸、常滑をいいます。
信楽
信楽焼は、現在の滋賀県甲賀郡信楽町で焼かれた陶器で、12世紀の末、平安時代末から始められたと考えられます。
信楽焼きは須恵器の流れをくみ、無釉、焼締め陶器です。
無釉と言っても、炎が強烈に当たった部分には、自然の灰が降り、それが摂氏1300度前後の炎の中で溶け、ビードロとなり、自然釉となっているものも少なくない。
焼成品目は、すり鉢、壷、甕の三種を主とした雑器でした。
この頃の陶工は、半農半陶で、農閑期に焼き物を作る仕事に従事していました。
窯跡は100基を超えるといわれているが、その殆どは未調査のまま荒れ果てています。
備前
備前焼きも信楽同様、須恵器の流れをくみ、十二世紀の末から始まったと考えられています。
現在の岡山県備前 市近郊で焼かれた焼き物で、信楽と同じように、すり鉢、壷、甕の三種を主とした雑器でした。
殆どの産地がそうであるように、室町時代の末になって茶の湯が盛んになってくると、茶器の生産を始めるようになるのは、備前とて同様でした。
丹波
丹波焼きは兵庫県多紀郡今田町立杭近辺で中世以来焼き続けられています。
中世の三種の器、壷、甕、すり鉢が 焼かれていたが、ここ丹波では、すり鉢が非常に少なく、江戸に入ってから多く焼かれるようになります。
丹波も、信楽、備前同様、須恵器系に属しています。
信楽、備前、丹波の各窯場の関西地方に位置する窯場は、須恵器の系列に属しています。
越前
越前焼きは福井県武生市の北西に位置する織田町、宮崎村を中心に焼かれていました。
北陸にはこの他にも加賀、珠洲、狼沢(おうえんざわ)の窯があります。
越前は、基本的には須恵器系に属するが、瀬戸の白瓷の影響も受け中世には瓷器系にも属し、前に述べた信楽、備前、丹波とは少し異なります。
製品は甕、壷、すり鉢等の生活雑器を中心に、現在まで引き継がれています。
瀬戸
瀬戸は、白瓷の系譜に属する施釉陶器で、現在の愛知県瀬戸市で連綿と続いています。
瀬戸は中世古窯における唯一の施釉陶器を製造し独自の道を歩んでいます。
従って、中世古窯においては殆どの窯場が甕、壷、すり鉢の三種を焼成していたが黄緑色や黒褐色の釉薬を使った壷や瓶子、山茶碗を焼成していました。
常滑
常滑焼の経緯は瀬戸の猿投窯の衰退と常滑古窯の発生とが大きく関わっています。
常滑の位置する知多半島には、3000基の窯が確認されているといいます。
現在最も古いと確認しているものは、三筋壷と同時に発見された四方仏石の刻文に天治2年(1125年)とあったものです。
常滑も、ほかの中世古窯と同じように、すり鉢状の鉢、甕、壷の日常雑器が主体でした。
沈寿官(ちんじゅかん)
薩摩焼の苗代川(なえしろがわ)系の朝鮮陶工。沈家は藩用の白薩摩を製作しており、当代14代目では金襴手(きんらんで)や透し彫りが特徴。
つ
肩衝茶入、「付藻茄子」(つくもなす)
和名「付藻茄子」(つくもなす)という中国で出来た茶入が有り、日本に渡り足利義満が所有していましたが、その愛蔵ぶりは度が過ぎていて、戦場に行く時も肌身離さないで鎧びつの中に特別の収納場所を作って戦におもむくほどでした。
その後、これを茶人「珠光」が買い、「朝倉太郎左衛門」から「松永弾正」に渡り、さらに時の権力者「織田信長」の機嫌とるために弾正から信長に献上され信長が茶会にしばしば使った記録があります。
安土城から本能寺に持ち込まれて、おそらくはこの茶入を主役とした茶会が開催されたと思われるが、その終了数時間後に「明智光秀」乱入の変の合い本能寺が焼け落ちたときは、かろうじて何者かが持ち出したため、なぜか無事であったようです。
変事の後、茶入は「豊臣秀吉」が所有する所となり、後に「徳川秀頼」に渡ったが、元和元年、「徳川家康」に攻められて大阪城の宝庫と共に焼けました。
家康は灰の中を探させ、いくつかの名器を探し出して見事に修復した「藤重藤元」にこの茶入を与えました。
この頃の茶入の価値の重さは、「石田光成」拳兵の報を受けて家康が兵を西に返した時、側近の某が今度の大阪攻めでは茶入の名品が沢山手に入りましょうから、軍功をたてたらそのうちのひとつを拝領したい、と申し出たという言い伝えからも、領地同様の価値観があったと思われます。
この「付藻茄子」(つくもなす)は、徳川家康よりの拝領とあって、江戸時代の間は藤重家から外には出る事もなかったのですが、明治九年四百円で岩崎家に入り、現在、静嘉堂に伝わっています。
室町時代以来、動乱に世のほとんどすべての政治経済の実力者の寵愛をほしいままにし、歴史的戦火をかいくぐって生き残った名器ですね。
土見せ(つちみせ)
釉を掛け残して、土味を見せることで、茶碗の高台回りなど釉薬(ゆうやく)が掛からない部分。
素地(きじ)が見ることができるため見所の一つとなります。
土型(つちがた)
土で作られた型のことで、棒で叩きながら形を作る「型打ち」と粘土板を型にかぶせる「糸きり細工」の2通りあります。
土でつくられた成型用の型のことで、型打ち技法・糸切細工のとき使われるます。
現代では石膏でつくられることが多い。
筒型茶碗(つつがたぢゃわん)
円筒形の胴をした茶碗。深いものは深筒、浅めのものは半筒。
筒描き(つつがき)
竹や藁など筒状のものに入れた泥奬や釉(うわぐすり)で、文様を描くこと。
筒形(つつがた)
ある程度の深さがあり、円形や角柱形が多く、扇形や花形などもある向付(むこうづけ)の器形。
鍔縁(つばぶち)
平鉢などの口縁が帽子のひさしのように横に張り出しているものをいう。
壺屋焼(つぼややき)
沖縄県那覇市壺屋で焼かれた陶器。南蛮焼の技法を取り入れた荒焼と、朝鮮人陶工により開窯した上焼がある。
鶴首(つるくび)
徳利や花生などにある、首が鶴のようにすらっと長い器形。
て
低火度(ていかど)
800~900度の低い温度で焼成すること。
定窯(ていよう)
優れた白磁(はくじ)を焼いた、中国河北省にある宋代の名窯。
定窯は宋時代を代表する白磁の名窯であり、窯址は現在の河北省曲陽県に発見されています。
良質の磁土を用いて器壁は薄くのびやかに成形され、酸化焔焼成によって釉薬中の微量の鉄分が黄味をおび、あたたかみのある牙白色の釉膚となっています。
流麗な蓮花文、文様の輪郭に向って斜めに刃を入れて彫る片切り彫りの手法によっており、深く掘られた部分に釉薬が厚く溜ることによって文様が浮かび上がって見えるのです。
釉調の美しさと文様の見事さをかねそなえた定窯白磁の典型作といえます。
鉄絵(てつえ)銹絵(さびえ)
酸化第二鉄や鬼板(おにいた)など、鉄の顔料を用いて得付けしたもので、銹絵(さびえ)ともいう。
下絵付けで、鬼板などの鉄分を多く含む顔料で描く技法。
銹絵(さびえ)や鉄砂(てっしゃ)と同じだが、鉄砂の場合は釉薬を意味することもあります。
鉄絵は透明釉の下に描かれる釉下彩の一種です。
酸化鉄による呈色のため、黒褐色の絵文様となります。
鉄釉(てつぐすり・てつゆう)
青磁釉、黄瀬戸釉、天目釉、柿釉(かきゆう)、飴釉(あめぐすり)、黒釉(こくゆう)など鉄を含む釉薬(ゆうやく)で、鉄分が多いほど黒色に近い。
手捻り(てびねり)手捏ね(てづくね)
轆轤(ろくろ)を使わず、粘土を手で延ばしながら成形。
手造りともいい、指先だけで成形する方法をいう。
楽焼(らくやき)はこの方法により、素朴で雅致に富んだ茶碗をつくった。
天狗谷窯(てんぐだにがま)
佐賀県有田町の白川谷にあった連房式登窯。染付(そめつけ)や青磁(せいじ)の碗、皿などが出土し初めて磁器が焼かれた窯。
天啓赤絵(てんけいあかえ)
中国景徳鎮(けいとくちん)の、民窯で焼かれた粗製の色絵磁器。赤、緑、黄で古染付(こそめつけ)のような簡略な絵が特徴。
天目(てんもく)油滴天目(ゆてきてんもく)曜変天目(ようへんてんもく)
鎌倉時代、中国の浙江省天目山で使われていた茶碗が日本に到来しました。
天目山の茶碗ということで「天目」と言われます。
天目茶碗の中でも最も重視されるのが七種の天目です。
建盞、烏盞、曜変、灰被、油滴、黄盞、玳皮盞の七種の天目を言います。
曜変天目(ようへんてんもく)茶碗は、中国、建窯でつくられた天目茶碗の一種。
黒色の茶碗の内面に青紫色の光彩に覆われた星文と呼ばれる円状の小斑文が散在する。
遺品は日本にある3点のみで、全て国宝の指定を受け静嘉堂文庫(「稲葉天目」)、藤田美術館、大徳寺龍光院に収蔵されています。
天竜寺青磁(てんりゅうじせいじ)
中国龍泉窯で元から明時代にかけて作られた青磁で、釉色がやや沈んだ暗緑色の青磁のことです。
その名は、京都の天竜寺にこの手の青磁の香炉があったからとも言われています。
と
陶器(とうき)
粘土を主原料とし、非透光性で若干の吸水性がある焼物で、焼成温度が土器より高く、非透光性で若干の吸水性がある焼き物。
主な産地としては、唐津・萩・備前・信楽・常滑など
陶工(とうこう)
陶磁器の製作に携わる人。陶芸家・陶芸作家に対する言葉。
唐三彩(とうさんさい)
中国唐時代に焼かれた、低火度鉛釉(ていかどえんゆう)を使った貴族文化を象徴する華やかで多彩色の焼き物。
籐四郎(とうしろう)
瀬戸焼(せとやき)の祖、加藤四郎左衛門景正(かとうしろうえもんかげまさ)の通称。
陶石(とうせき)
磁器の原料であり、日本では佐賀県有田町泉山の陶石(とうせき)の発見が最も早い。
陶磁器の原料になる白色の岩石で石英、絹雲母を主成分とします。
リソイダイトと呼ばれる岩石が変質したもので「陶石」というのは窯業上の俗称です。
陶胎(とうたい)
素地が陶器の原料であるもの。
多くは白土をもって化粧がけがされ、貫入が全体に入る。
唐三彩(とうさんさい)
中国の唐時代につくられた軟陶三彩を呼びます。
緑・白・褐の三色が多いが、緑なり、白なりの一色のものもあります。
たまに青色を加えたものもあり、これは藍彩と呼ばれています。
殆ど副葬品として用いられました。
透明釉(とうめいゆう)
1300度前後の焼成で透明になる釉薬。
灰釉(かいゆう)に長石(ちょうせき)や珪石(けいせき)やカオリンを混ぜた釉(うわぐすり。
鍋島では柞灰(いすばい)を主原料として調合しています。
土器(どき)
粘土を材料として、成形・焼成された容器。
縄文土器、弥生土器、土師器(はじき)など。
兜巾(ときん)
兜巾高台などというが、高台中央部が突起をなしているもののこと。突起の形が山伏のかぶる兜巾に似ていることからこの名がついた。
カンナで高台を削るときに中心が高くなることからこのような形状に削れます。
常滑焼(とこなめやき)
平安時代後期より愛知県常滑市で作られた焼締陶。土は締まって、濃緑の自然釉(しぜんゆう)が流れるのが特徴。
トチン(とちん)ハマ(はま)
肥前の登り窯は床が平坦でなく斜面であったため、まずトチンを置きその上に器物を乗せて焼いていた。
又器物が大きいとその中間にハマをしいて焼いた。
土とち、目土などとも呼ばれる窯道具。
作品を重ねて焼く場合、釉が熔けて作品同士や棚板とくっつかないように、土で玉などをつくり、作品のあいだに挟んだり、棚板から浮かせたりします。
魚屋(ととや)
高麗茶碗(こうらいぢゃわん)の中の御本茶碗(ごほんぢゃわん)の一種で、平茶碗の形が多く高台は小さい。
ととやは魚屋とか斗〃屋とも書く李朝の茶碗で、名称の由来は堺の豪商魚屋(渡唐屋)が朝鮮から取り寄せた事からとか、利休が魚商の店頭で見出したとか諸説あります。
土灰(どばい)
雑木を燃やした灰で、これを水で洗ってアク抜きをしている釉薬(ゆうやく)の溶剤。
飛び鉋(とびかんな)
轆轤(ろくろ)でヘラを当てて、粘土に軽くひっかけるようにして回すと一定の間隔にできる模様。
小鹿田焼で特徴的な技法「飛び鉋」は蹴轆轤を回しながら、生乾きの化粧土に鉄の小さな鉋の先が引っ掛かるようにして削り目をつける技法です。
バーナード・リーチが興味と関心をもちながら製法が分からなかった「飛び鉋」が、小鹿田焼で用いられていたことに驚き、その製法を学びとったことが『日本絵日記』(バーナード・リーチ著)に記されています。
砥部焼(とべやき)
1730年頃、愛媛県砥部町で日用雑器の窯として始まった。
九州系の磁器の技術が導入され、染付磁器(そめつけじき)が中心。
富本憲吉(とみもとけんきち)
大正2年、バーナード・リーチとの出会いによって陶芸家への道を歩み始めた富本憲吉は、郷里大和川河畔で写生中、農家の軒下で犬の餌入れに使われていた白磁鉢に強い影響を受ける。
それがきっかけで、李朝白磁への関心が高まり、朝鮮行きを決意する。
柳宗悦から浅川伯教・巧兄弟を紹介され、李王家博物館や各地の窯場を見学して廻る。数々の名品や名工との貴重な出会いから多くを学び、かつ模倣に沈むことなく自分の方向を探っていきました。
帰国して、彼独自の白磁が姿を現わしてきました。
白磁(はくじ)・染付(そめつけ)・色絵(いろえ)・金彩(きんさい)に優れた作品を残しました。